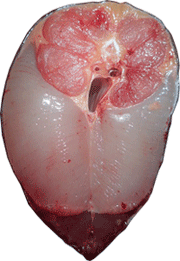|
1818 小説「フランケンシュタイン、すなわち近代のプロメシュース」 Frankenstein: or The Modern Prometheus
北極探検の航海に出た青年ウォルトン船長が、平穏に暮らすロンドンの姉に手紙を送る。読者は、手紙の受手である姉の立場に立って、ウォルトンの手紙を読むこととなる。この世の読者を、あの世の異常な物語に導入する手法である。 ●ウォルトン船長 北極点を目指す探検家。現実世界の常識を忘れて、想念世界にこもり高揚している。 |
イングランド サヴィル夫人宛 1711年12月11日 ペテルブルクにて 昨日こちらに着きました。そこで手初めに、ぼくの愛する姉上に安心してもらおうというわけです。ぼくは元気です。そして、この企ての成功にますます確信を強めています。 ここはもうロンドンのはるか北。ペテルブルクの街なかを歩いていると、冷たい北の微風が頬にたわむれて、神経をひきしめ、ぼくを喜びで一杯にしてくれます。この気持、姉さんにわかるだろうか? これからおもむく地域から渡ってくるこの風は、あの凍てつく気候の予感をぼくに運んでくれるんです。この約束の風にあおられて、ぼくの白昼夢はいよいよ熱をおび、生き生きとしてきます。極地は氷ばかりのさびれた場所だと思いこもうとしても、だめなんだ。 空想に現われる北極はいつも、美と歓喜の地。そこでは、太陽がつねに見えている。大きな日輪がちょうど地平をかすめながら、永遠の輝きを放っている。 そこでは雪も氷も追いはらわれて、凪いだ海を船で渡れば、人の棲む地上でかつて発見されたどんな土地にもまさる、不思議で美しい陸地に行くことができるのです。 |
船長は北極海で、流氷の上でそりに乗ったまま漂流しているヴィクターを救って船に乗せてやる。その男は、たった一人で北極海にいる、異常な身上話を船長に物語る。 ●ヴィクター・フランケンシュタイン 医学生 |
|
私はスイスのジュネーヴの名門の家の長男として生まれた、ヴィクター・フランケンシュタインという者です。子供のときから何一つ不自由なく、両親の愛情の下に平和に育てられました。 家は共和国でも屈指の名門のひとつです。先祖は顧問官や地方判事を長年やっていましたし、父も公職にいくつもついて名誉と評判を得た人でした。父を知る人はみな、その高潔な人柄と公務へのたゆまぬ専心ぶりを敬いました。若い日を国の仕事に追われて過ごし、またいろいろ事情もあって、早い結婚はできず、夫となり一家の父となったのは晩年も近づいてからのことでした。 優しい母の愛撫と、父が私を見るときの慈しみあふれる微笑が、私の最初の思い出です。私はふたりの玩具、ふたりの偶像、ふたりの子供。天からさずかった弱い生き物。 良い人間に育て、将来を幸せにしてやるも不幸にするも彼らしだい。この子への義務をどう果たしおおせるかで決まるのです。こんなみずから生命をあたえた子への義務の自覚の深さに加え、活発な思いやりの精神に富む父と母でしたから、幼児期のすべての時間を通じて私が忍耐と慈愛と自制の心を教えこまれたことは、ご想像いただけるでしょう |
インゴルシュタットの大学1793年 機械的工程としてコントロールされた出産。蘇生装置 スチームパンクの子宮 ガルバーニ電気 誕生した生き物は、理想とはほど遠く、見れば嫌悪感を抱かずにはいられないほど醜い[名もない生命体]だった。 ●クレンペ 医学教授 |
|
大学で自然科学を専攻しました私は科学、特に化学に対する向学心に燃え、一心不乱に勉学に励みましたが、その熱意のあまりとんでもない野望にとりつかれてしまったのです。無生物に生命の火を灯すことを、科学の力で可能ならしめたいものだ。 そこで私は下宿のてっぺんの部屋で、こっそり実験を始めました。解剖室や屠殺場から死体の断片を持ち込んで、いろいろ試みているうちに、遂に私が完成させた人造人間が生命を持つようになったのです。 11月のとあるわびしい夜のことでした。苦しいほどの熱意に駆られ、私は足もとに横たわる命のない物体に生命の火花を吹きこむべく、生命の器械をまわりに集めました。目が開き、呼吸をし、手足を動かしはじめました。 すでに午前一時。雨がぱらぱらと陰気に窓を打ち、蝋燭は今にも燃えつきようとする、そのとき、なかば消えかけた微かな光に、私は生き物のどんより黄色い目がひらくのを見たのです。それは重く息をつき、痙攣が手足を走りました。 この大詰めの私の感情を語ることなどできるでしょうか。どう描いたらいいのでしょう、計り知れぬ苦心と用心をかさねて創りだそうとしてきた、このあさましい生き物は、黄色い皮膚は下の筋肉や動脈の作用をほとんど隠さず、おぞましくきわだたせるばかりでした。はめこまれた薄茶の眼窩とほとんど同じ色に見えるうるんだ目、やつれたような顔の色、一文字の黒い唇を。 実験が成功した途端、この醜悪怪奇な生物が動き出した途端、私は喜ぶどころか、大変な嫌悪感に襲われ、まるで悪夢にうなされているかのように、部屋から逃げ出してしまい、その夜は家に戻る勇気が出ませんでした。 翌朝、おそるおそる私の部屋に戻ってみると、[名もない生命体]はおらず、部屋は空っぽのままでした。私はほっと安心した途端に、これまでの精神的肉体的な疲労と緊張の反動からでしょうが、どっと重い病気になってしまいました。 夢。健康ではちきれそうな婚約者エリザベスが、インゴルシュタットの街を歩いているのを見たように思い、私は驚き喜んで彼女を抱きしめます。 ところがその唇に最初のキスをあたえたとたん、それは死の鉛色に変わってしまうのでした。面立ちも変わって、私は死んだ母のなきがらを腕に抱いているようでした。 経帷子[きょうかたびら]がからだを包み、フランネルの襞を蛆虫が這っているのが見えました。恐怖にぞっとして目をさますと、冷たい玉の汗が額をおおい、歯はガチガチと鳴り、手足はことごとくひきつっていた、 そのとき窓のよろい戸の隙間からさしこむおぼろな黄色い月明かりに、私はあいつを見たのです。私が創造した破廉恥な[名もない生命体]を。そいつはベッドの帳をかかげていて、あれが目と呼べるものなら、じっと私を見ていました。 あごをひらいて何やらわからぬ音を出し、歯をむいて頬に皺を寄せました。しゃべったのかもしれない、だが私は聞いていませんでした。片手を伸ばして押しとめようとするらしいのを、逃れて一目散に階下へ駆けおりました。人の身であの顔の恐ろしさに耐えうる者はおりますまい。 回復して歩けるようになったら、勉強を中断してジュネーヴのわが家に帰ろうと思っていたのですが、その時私のいないわが家で恐ろしい事件が起こりました。戸外で遊んでいた私の小さい弟が、何者かに惨殺されてしまったのです。 私がジュネーヴに戻ってみると、召使いのジュスティーヌが容疑者として捕らえられていました。しかし私は、弟を殺したのは、ほかならぬ私自身の造った[名もない生命体]であることを知ってしまったのです。 私は悩みました。私が行った神をおそれぬ仕業を皆に打ちあける勇気はとてもありませんでしたし、かりに真相を話しても、誰も私の言葉を信じてはくれないでしょう。私の気が狂ったとしか思いますまい。しかし、その一方ジュスティーヌが無実の罪で死刑にされるのを、むざむざ見殺しにすることも、とても耐えられません。 私はエリザベートと一緒に彼女を慰め、彼女の無罪を立証するべく必死の努力を始めますが、状況証拠が彼女に不利なため、とうとう裁判で有罪と宣告され、処刑されてしまいました。 私は真相を打ちあけなかった自分の卑怯を自ら責める気持で、半狂乱でした。エリザベートをはじめ、誰もが私を慰めてくれましたが、もちろん弟の死の責任が私にあることは知るはずもありません。父は私の病気がまだ完治していないと思い、病気が治り次第私とエリザベートを結婚させ、私の精神を安定させようと考えました。 そうしている間にも、あちこちで謎の事件が起こります。人びとは五里霧中ですが、その下手人があの[名もない生命体]であるということを、私にだけ画知っていました。 |
[名もない生命体]は、美しい精神と、醜い身体のずれてしまった人々の象徴となって、底知れぬ恨みを蓄積していく。 ●ド・ラセー パリで不幸な事件に巻き込まれてフランスを追放された盲目の老人 |
責任を感じた私は、[名もない生命体]に会うため、モンブラン北壁メール・ド・グラース氷河へ出かけ、そこで[名もない生命体]と対決した。 「失せろ そのいやらしい姿がおれに見えないところへ、行ってしまえ」 私はその手を力まかせに払いのけました。そして、私は[名もない生命体]の口から意外な、しかし恐ろしいことを聞かされたのです。 概念は知覚の視覚的成分・触覚的成分・音響的成分により学習される。 自分の生涯の初期のころを思い出すのは、かなり骨の折れることだ。あのころの出来事はみな入りみだれ、ぼやけて見える。数知れぬ不思議な感覚が自分をとらえた。自分はいっぺんに見、触れ、聞き、嗅いだ。そしておのおのの感覚の働きを識別できるようになるまでには、じつに長い時間がいったのだ。 だんだんと強い光が神経を圧迫しだしたので、目をつぶらずにはおれなかったのを覚えている。そうすると暗闇がせまってきて、自分は不安になった。だがそう感じるまもなく、今思えば目をひらいたのだったろうが、またもや光がどっと射してきた。自分は歩いた。それからおりたように思う。 私の部屋を飛び出した[名もない生命体]は、決して人間に敵意を持っていたわけではないのです。むしろ淋しがりやで、人間とつき合いたい、人間に愛されたいと願っていました。ところがその醜悪な形のために、出会う人間のすべてから憎まれ、攻撃され、顔をそむけられ、逃げられてしまいました。 しばらく森で木の実を食べて暮した[名もない生命体]は、食べ物を求めて人の住む村へ来てしまう。 自分の姿を透明な池のなかに見たときの恐ろしさは 一瞬自分はぎくりと身をひいた。鏡に映ったのが本当にわが身であるとは信じられなかったのだ。そして自分が現実にこのとおりの[名もない生命体]であると納得するにいたったときには、落胆と屈辱のにがい思いがこみあげてきた。よく湖や泉に映る自分の姿を見た時など、思わず自己嫌悪と恐怖の念にかられて顔そむけた。 こわごわ一軒の屋根の低い小屋のなかににげこんだのだ。がらんとして、村の大邸宅を見たあとでは見るからにみじめなものだった。それでもこの小屋にくっついて小ぎれいで気持よさげな田舎家があったのだが、ついさっき村で手痛い経験をしたばかりだから、そっちへ入る勇気はなかった。 自分の隠れ家は木造りで、ただ屋根が低いため真っすぐ坐るのがやっとだった。地面には木を敷かず地べたがそのまま床だったが、かわいているし、無数の隙間から風が入ってくるとはいえ、雨や雪をしのぐ場所としては悪くない。 自分の住処を調べてみると、その一部がもと母屋の窓になっていたのを、板でふさいであるのが見つかった。一か所に小さくてほとんど人目につかない、ちょうどむこうが見えるくらいの隙があり、この穴から、しっくい塗りの清潔だが家具がなくがらんとした小部屋を眺めることができた。 [名もない生命体]は、田舎家の母屋に隣接した狭い納屋の中に引きこもり、壁の隙間から、母屋に住む人々の暮らしを貪るように覗き見て日々を過ごす。まるでミニチュアのドールハウスをうっとり眺めて夢見る人のように。あるいは、まるで孤独な人がテレビの向こうの幸せな世界に憧れるように。 田舎家の主は目の見えない老人ド・ラセーの一家は、互いを優しくいたわりあって生きていた。ド・ラセーの一家の完璧な姿かたちに自分は感嘆したものだ。その優美さ、その美しさ、繊細な肌の色。 ある時、フェリックスの恋人であるトルコ娘サフィーがはるばるやって来て、彼らと暮すようになり、彼らはサフィーにフランス語を教える。それをいつも壁の隙間から覗いている[名もない生命体]は、流暢なフランス語を身に付けることができたのだった。 自分はド・ラセーの一家を自分の未来の運命を決定する、よりすぐれた存在として眺めていた。空想のなかで幾度となく、彼らの前に姿を見せ、受け入れてもらうときの図を描いた。彼らは嫌悪をもよおすだろう、だがやがて自分の優しい振舞と友好的な言葉とで、まずは好意を、それから愛をかちえることができるだろうと想像した。 森のド・セラー家での自己教育。 一家の人々の徳と善意を自分はたたえ、上品な物腰と温和な気質を自分は愛した。だが、彼らとの交際から自分は閉めだされていて、できるのは見られもせず気づかれもせず、こっそり近づくことだけだった。仲間の一員になりたいという願いは、それで満足させられるどころか、かえってつのる一方だった。 ある夜のこと、地面に革の旅行鞄があるのを見つけた。なかには衣類が数点と数冊の書物が入っていた。自分は夢中で獲物をつかみ、それを納屋に持ち帰った。さいわい書物は自分がこの家で初歩を学んだ同じフランス語で書かれていた。 それは「失楽園」「プルターク英雄伝」「若きウェルテルの悩み」とからなっていた。この宝を持つ嬉しさはたとえようもないものだった。これらの本の影響はとても語りつくせない。それは新しい概念や感情をかぎりなく心に生みだした。 「若きウェルテルの悩み」では、単純で胸を打つストーリーが面白かったというほかに、自分にはそれまでわかりにくかった諸問題についてさまざまな見方が考察され、いろいろの光が投げられたので、この本は思索と驚異のつきることのない泉となった。 小屋に着いてすぐのことだが、ヴィクターの実験室から持ってきた服のポケットに、なにやら書類が見つかった。初めは気にもかけなかったが、書いてある文字が判じられるようになったものだから、せっせとそれを勉強しはじめたのだ。それは自分の創造にいたるまでの四か月間の日記だった。 この身の呪われた起源にかかわることがひとつ残らず書いてある。読んでいるうちに吐きたくなった。この身が生を受けたその日が憎い苦しさのあまりにおれは叫んだ。呪われた創り主よおまえまでがむかついて顔をそむける、そんなおぞましい[名もない生命体]を、なにゆえに創り出したのだ。 [名もない生命体]は、目の見えないド・ラセー老人が一人でいるとき、ついに愛の告白をする。 「私は不幸な、見捨てられた者なのです。まわりを見ても、地上に縁者も友もいない。これから訪ねる優しい人々は私をまだ見たことがなく、ほとんど知ってもおりません。私は不安でたまらない。そこでうまくいかなかったら、永久に世界ののけものになってしまうのですから。私は善良な性格で、今まで害もなさずに生きてきた。人助けも少しはしました。それなのに致命的な偏見があの人たちの目を曇らせていて、心ある優しい友を見るべきところに、忌わしい[名もない生命体]しか見ないのです」 「それはなんとも運の悪い――だがあんたに罪がないのが本当なら、偏見を除くことはできないのかね」 ちょうどそのとき、フェリックス、アガサ、サフィーの足音がした。一刻の猶予もならなかった。自分は老人の手をつかんで叫んだ。「今ですどうか守ってください あなたがた一家が、私の訪ねてきた友人なんです。この試練のときに、私を見捨てないでください」「何だって」と老人は叫んだ。「あんたはどなたです?」 フェリックスとサフィーとアガサが自分を見たときの恐怖と動転ぶりは言語を絶するものだった。アガサは気絶し、サフィーは友を介抱するどころではなく、戸外に飛びだした。フェリックスは突っこんできて、人間わざとは思えぬ力で、自分をむしゃぶりついた父親のひざからもぎ離した。彼は怒りに逆上して自分を床にたたきつけ、棒きれで力まかせにひっぱたいた 自分の生みの親への恨みがつのる一方で、ド・ラセーたちに愛してほしい気持は一層つのる。心はこの愛すべき人々に知ってもらいたい、愛されたいとあこがれた。あのうるわしいまなざしが愛をたたえてこちらに向けられるのを見ることが、自分の究極の野心であった。 世にある無数の人間のなかに、おれを哀れみ、助ける者はひとりもいない。敵に対して優しい心を持てというのか? 否。その瞬間から、おれは永遠の戦いを宣言したのだ。人類に、そしてとりわけ、自分を創り、このしのびがたい苦悩のなかへ送りだしたその男に。 一方的に人間から悪意と攻撃の矢を浴びている日が続くにつれ、孤独と絶望から遂に[名もない生命体]は創造主たるヴィクターを怨み、呪い、復讐を誓うようになってしまった。 そして孤独に苛まれ、愛に飢えた[名もない生命体]は私に迫るのでした。 そういう生き物を創ってもらわなくてはならぬ。自分のために女を創造してもらいたい。ともに暮らして、生きるのに必要な心の共感を交わせる相手を創ってほしい。それができるのはあんただけだ。おれと性の違う、同じくらいおぞましい生き物を創れと言うんだ。満たされるものはちっぽけだが、受けとれるものはそれしかないのだから、それでおれは満足しよう。 なるほど自分たちは[名もない生命体]で、世界じゅうからつまはじきにされるだろうが、それでおたがいいっそう深く結ばれることになるだろう。幸せな暮らしはできまいが、害もなさず、今のようなみじめさは味わわずにすむだろう。おお、わが創り主よ、幸せにしてくれ、ひとつだけでも恩を受けたと、感謝させてくれ おれに同情を寄せてくれる生き物もいると、見せてくれ。この頼みをはねつけないでくれ 「おれが生きるに必要な同情を交換し会うために、女の人造人間をおれのために造れ。それが出来るのはお前だけだ。それをおれは当然の権利としてお前に要求するのだ」 「おれが永久に人の住む地を去って害のない暮らしをおくるか、あんたたち人類の鞭となり、あんたにもすみやかな破滅をもたらすか、それはあんたしだいで決まるのだ」 |
|
ヴィクターは、女の[名もない生命体]を創ることを一度は承知するが、彼を思いとどまらせるのは、女の[名もない生命体]は自己増殖するという恐るべき事実である。 |
今また別の生き物を創ろうとしているが、その性質について無知なのは今度も同じでした。あるいは連れあいより一万倍も性悪で、殺人や悪行をそれだけのために喜ぶかもしれない。人の住む地を去り、荒野で暮らすとあいつは誓ったが、こちらは違う。女のほうも思考のできる理性ある生き物になるはずだが、自分の創造以前に交わされた契約などには従わないと言うかもしれない。 彼らがたがいを憎むことさえありうるのだ。すでに生きている[名もない生命体]は、わが身の醜さをいとわしく思っており、それが目の前に女の姿で現れたなら、いっそう激しい嫌悪を抱きはしないだろうか。相手もまた彼を嫌って、よりすぐれた人間の美を求めようとするかもしれず、女は去り、彼はまたひとりになって、自分と同じ種の生き物にまで見棄てられたと新たな怒りを燃やすことになるかもしれない。 私は[名もない生命体]を哀れに思い、自責の念を感じましたが、この要求に応ずるわけにはいきません。もし[名もない生命体]に妻を造ってやって、その後次々に子孫が生まれたらと。考えるだけでもぞっとしたからです。 こうしてヴィクターは、ほとんど完成していた女の身体をずたずたに引き裂いてしまう。 ふと顔をあげた私は、月明かりの窓辺にあの悪魔の姿をみたのです。ぞっとするような笑みに唇をゆがめ、自分の課した仕事を私が坐ってやりとげるのを眺めていました。そうです、そいつは私の旅についてきていたのです。見ていると、その顔にはこのうえもない悪意と裏切りの色が浮かびました。 [名もない生命体]は私に復讐を誓い、その後私の身の上に次々と不幸が訪れました。そしてエリザベートとの結婚の日が近づくにつれて、私の不安は増々強くなりました。なぜなら、[名もない生命体]は「お前の結婚の夜、おれはお前のところに行ってやるからな」と脅迫していたからです。しかも私の不安を誰にも、最愛のエリザベートにすら知らせることができない私の苦悩はどんなだったでしょう。 遂に私はエリザベートと結婚しました。が、その晩、幸福は一気に不幸のどん底へと転落しました。[名もない生命体]が彼女を殺してしまったのです。 絶望にもだえ、[名もない生命体]に殺されてしまった妻エリザベスを見おろしていたときに、私はふと顔をあげました。部屋の窓は前には閉まって暗かったのが、薄黄色の月の光が部屋を照らしだしているのにぎょっとしました。窓はあけ放されていました。私をおそった恐怖は、とうてい口では言えません。ひらいた窓のところに、世にもおぞましい、憎むべき姿を見たのです。 [名もない生命体]は顔に笑みを浮かべ、嘲笑うように、むごたらしい指で私の妻の亡骸をさしてみせました。私は窓に駆けより、胸の拳銃をひきぬいて、発射しました。が、敵は身をかわしてその場から跳びのくと、稲妻のようなすばやさで走りさり、湖に飛びこんでしまいました。 人間を殺すことが、自分の最大の苦痛を取り除くことであり、それゆえ最高の善なのだ。 (ケネス・ブラナ映画の場合、エリザベートの頭脳が肉体を焼き消滅する ) |
ウォルトン船長の手紙 |
絶望と復讐の炎で燃えさかる私は、たとえ世界の果てまでであろうとも、あの[名もない生命体]を追いつめ破壊する決心でした。そして遂にロシアの北端へ、さらにそこから犬ぞりに乗って張りつめた氷の海を北極へと向かったのです。そりを曳く犬は次々にと倒れて行きました。そして突然氷が割れて私は流氷の上に置き去りにされました。 「ウォルトン船長、あなたの船が南ではなく北に向かおうとしていると聞いて、私は狂喜しました。いよいよ私の追跡も終わりになる時が来ました。私の最期も近いと思います。もし私が仕事を果たさずして倒れたら、どうかあなたが私の代りにあの[名もない生命体]を仕とめて下さい。お願いです」。 しかし、氷山に閉じ込められ、危険が迫るにつれて、危険を覚悟で志願して来た船員たちも恐怖のために動揺し、ウォルトン船長に、もし氷山から脱出できたら即時北極行きを断念して、南に向かって脱出せよ、と強硬な要求をつきつけて来た。 次第に弱って行くヴィクターの残っている船室に船長が入って行った時、彼は世にも恐ろしい[名もない生命体]が病人の上にのしかかっているのを見た。すでにヴィクターは冷たくなっていた。 [名もない生命体]は恐怖のために身動き出来ない船長に向かって、こう言った。これでおれの仕事は終わった。これ以上不必要な罪を犯すつもりはない。だからお前たちには何の危害も及ぼさないから安心せよ。おれはこれから氷の筏に乗って北極に向い、そこをおれの墓場とするのだから。 おれをこの世に生み出した男は死んだ。だから、おれが死ねば、おれたち二人についての記憶もすぐに消えることだろう。 こう言い残すと[名もない生命体]は船室の窓から外に飛出し、姿を消した。 |