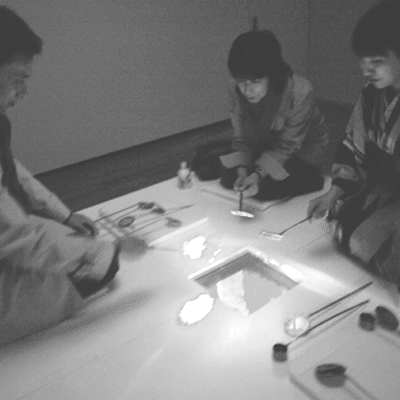|
共同研究報告書「情報芸術の研究」高橋士郎 →
1)研究の目的と成果
多摩美術大学情報デザイン学科の情報芸術コースAラボおよびBラボでは、毎年、学外展示会を企画実施して、その創作研究の成果を一般社会で発表してきた。情報芸術コースAラボおよびBラボの10年間合計25回におよぶを展示会の実績を研究事例として解析し、その歴史的意義を検討し、さらに、次世代の美術教育の目標を考察する。
調査した創作研究活動のデータは次のウエブサイトで公開している(ウェブマスタ:井上恵介)。
http://www.idd.tamabi.ac.jp/art/A-Lab/hac/
また関連する研究データベース"Hyper Art Catalog" を、次のウエブサイトで公開している(ウェブマスタ:高橋士郎)。
http://www.tamabi.ac.jp/idd/shiro/hac/hac.html
現代のデジタル情報技術は、相互方向性、媒体互換性、即時性、世界規模、動画配信ネットなどを可能とし、大量の情報を簡単に無償で伝達できる。さらに、ハイパーテキストのリンクは、リニヤな記述には出来ない、自由な連想を喚起し、より自然な思考方法に近づいているように思える。
しかしながら、上記のデジタル媒体は、著作権の確保に関しては全く無力である。著作権確保と発表既得権を担保するためには、アナログの印刷媒体が必要不可欠であるので、冊子「情藝研究」を編集し、1000部を出版配布した。

<図版1 表紙デザイン:工藤幸平>
冊子「情藝研究:Htper Art Catalog」多摩美術大学情報芸術コース10周年記念出版
発行:多摩美術大学情報藝術研究会
体裁:A4版白黒257頁カラ−カバ−付
「発表編」では、AラボおよびBラボが実施してきた学内外での展示会60会場の実施概要を記録した(編集委員:莇貴彦)。
「作品編」では、情報芸術コースの創作した作品55点を掲載した。各頁の画面構成は各作家から提供された自由な原稿形式に基づく。作品の分類方法として、古代ギリシャの四大元素(空気・水・土・火)を想定したが、物質の「気相」「液相」「固相」に続く、エネルギー(火)は現代的解釈により「光波」「電磁波」「重力」に細分した。また、非物質としての人間存在として「記憶」と「身体」を追加し、計8項目の分類とした。また読者がインターネットの検索サイトを応用して、最新かつ詳細な学習ができるように、関連するキーワードを付記した(編集委員:井上恵介)。
「理論編」では、大学院生や、研究室スタッフなどの論文19編および関連する資料を掲載した(編集委員:山本詠美)。
なお、今回の研究対象としては、20世紀の始めに発達した写真および映画などのメディアアートを創作領域とするCラボ( 指導教員:港千尋・佐々木成明)およびDラボ(
指導教員:原田大三郎)を除き、コンピュータ応用のニューメディアアートを創作領域とするBラボ( 指導教員:久保田晃弘・三上晴子)およびインスタレーションなどの現代美術を創作領域とするAラボ(指導教員:高橋士郎・森脇裕之)のみとした。
2)情報芸術コースの開設
<情報工学から情報芸術へ>
1989年、多摩美術大学美術学部が八王子へ移転した跡地の上野毛校舎に、美術学部二部が新設されるのを契機に、コンピュータの授業が企画され、当時はまだメインフレームとワークステーションの時代に、多摩美術大学は、設立草創のアップルジャパン社と4年間の産学共同研究の契約を締結してパソコンMac2を30台を購入した。
デザイン学科長に五十嵐威暢が就任、猪股裕一を中心としてパソコンによる美術教育のカリキュラム開発が始まった。また、須永剛司を中心としてヒューマンインタフェースの授業と、アンドレアス・シュナイダーを中心としたインターネットの授業が開始された。
現在では、日本のデザイン界の大半はMac党となっているが、当時のMacはプログラミングを知らない素人の機械という印象であり「大学でアップル社の消費者をつくるのか」と批評されたが、多摩美術大学のMac採用以降、日本の美術学校ではMacが主流となっていく。
本学とインターネットとの関わりは、1996年開催の仮想博覧会「インターネッ1996ワールドエキスポジション」の回線モニタとして始まる。翌年には学内にサーバーを設置してホームページの発信を開始した。
また、ウエブサイトの運営と平行して、印刷媒体を発行し、学内外にアピールした。1997年発行「news@tamabi第一号 」の内容は「飛ぶ学校、飛ぶメディア」伊藤俊治、
「多摩美術大学メディアセンター設立に向けて」高橋士郎、 「多摩美術大学でのデジタルの歩みとインターネット」猪股裕一 、「多摩美術大学附属美術館での情報活動への現状と構想について」小林宏道
、「多摩美術大学のネットワーク活動をお知らせするためのニューズレター」などである。1997年発行 「news@tamabi第二号」は「電脳空間から現実のドアへ吹き抜ける風」鈴木志郎康、「21世紀の情報建築家」須永剛司、「美術教育について」高橋士郎、「TOKYO
CONTINUUM」入江経一、「失われた部族」デビッド・ブレア、「情報の生態系」益田文和、「たった一言で」モーリス・バーンウェル、「ウェブサイト上のユーザー・インターフェイス・デザインとは」アーロン・マーカスなどである。1998年発行「news@tamabi最終号」は「新しいデザイン教育の構想 制作と知識の統合教育」須永剛司 、「無き影」港千尋、「動のブックマーク」古堅真彦、
「はじめてものをつくる」西村佳哲、「デザイン・カリキュラム」ステファン・メシュカット、「フェイスレス・インタフェース」小池英樹、「電子メール遊牧民」ガブリエル・コーンライヒュ、「東アジアからの新しいかおり」安尚秀、「ヘルワン大学と多摩美との共同研究」マクディ・アブデル・アジスなどである。
ところが、八王子校舎の建設のほうは、東京都の多摩ニュ−タウン計画の停滞が原因で一向に進行せず、1990年には現代美術の旗手東野芳明が闘病生活にはいってしまった。移転開始後20年の歳月を経た1994年に、ようやく八王子校地の隣接地購入が実現し、八王子校舎の建設が再開した。新校舎の設計と同期して学科改組が開始されたが、1996年に就任早々の秋山邦晴教務部長が急逝され、その後任に高橋史郎が教務部長および改組準備委員に就任することとなり、情報関連と環境関連の学科新設が研究された。著者の学生時代1960年代においては、コンピュータは反芸術の象徴であり、エコロジーはベトナム反戦の反体制運動であったが、180度のパラダイムシフトである。
以下は1996年に執筆された伊藤俊治の「情報デザイン学科の教育目標」の草案原稿である。
「21世紀に向け、世界的規模で加速化する情報化社会のなかで、必要な情報ソフト、なかでも映像や音響を有機的に組みあわせたマルチメディアソフトへの需要は急速に高まっています。こういった新しいマルチメディアは、映像や音響ばかりか、CG、テキスト,動画などの様々なメディアによる表現内容(コンテンツ)を、継ぎ目のないディジタルなメディアにのせて、世界中に伝達できる媒体ですが、同様にこれまでの表現技術も統合し新しい時代にふさわしい創造活動を切り開いてゆける可能性も秘めています。その表現形式も、鑑賞型のパッケージ・ソフト,インタラクティブ(相互的)なパッケージ・ソフト,ネットワーク型の作品、インスタレーションやスペース・デザイン,データベース型、VRを使ったサイバー・スペース方式など、多彩な領域に及び、応用ジャンルも、衛星通信から医療情報技術,電子出版,ホームショッピング,エンターテイメント・ビジネス,博物館展示、テレマーケティングまで広がっています。これらのメディアの融合による可能性を最高度に引き出して個性的な表現者、ディレクター、オペレーター、デザイナー、システム・エンジニア、プランナー、プロデューサーなどを養成するのが、この情報デザイン学科の役割です。情報やメディアをトータルにとらえ、絵画彫刻から映像音響、コンピュータ・ソフトウエアやインターフェイス・デザイン,都市計画から環境デザインに至るまで包括する新しい領域を設定し、実験的なプロジェクトやプログラムをたちあがらせてゆく教育の場、そこではメディアの融合や情報の交感が試みられ、それらの間を自由にゆききし、それを創造活動にフィードバックできる新しいタイプのクリエイターが羽ばたいてゆくことが期待されます」
ところが、本学で構想した当初の情報デザイン学科設置案は、美術学部でのコンピュータ関連学科設置の前例がないという理由で、文部省への申請が不可能となった。急遽、設置申請書類を書き直し、工学部相当のカリキュラム及び工学博士の教授を多数揃えての認可申請となった。1998年4月に開設した情報デザイン学科は、上野毛校舎での10年間におよぶMac教育の研究成果を発展させた上、情報工学を基礎とする美術教育となった。
ところが、 多摩美術大学に情報デザイン学科が新設された翌年の1999年には、早くも、武蔵野美術大学造形学部にデザイン情報学科が開設され、東京芸術大学美術学部の取手校地に先端芸術表現学科が開設された。そして10年後の2009年に、日本の大学に設置された情報デザイン学科は11校、デザイン情報学科は4校、メディアアートや先端芸術表現などの学科やコースは48校を数えるに至った。
3)学生作品のの考察
<インフォーメーションからコミュニケーションヘ>
情報芸術コースの学生達が創出してきた10年間のアートシーンを総括展望してみると、次の三つの傾向を指摘することができる。
a. 体感的コミュニケーション
古典的な絵画技法においては、空気感や重力感などのリアリティある表現が課題であった。額縁の中のキャンバス表層における芸術空間では、地球上の陸上生物が5億年を経て育んできた大気と重力の存在が欠如する。20世紀の抽象絵画は空気感と重力感を喪失してアンフォルメルとアンフラマンスに引きこもり、ともすると人間の野生感覚を超えたオカルト的な様相をみせる。数学者などが「美しさ」に感動する一方、芸術家は「美しさ」を憎悪するに至った。
文芸や絵画の想念空間でも、現実の物理科学を無視する不合理な表現がまかり通る。アリスやガリバーが縮小拡大しても、地球上の万有引力・空気の固有共振数・生物細胞の寸法などは縮小拡大せずに一定なのだから、アリスやガリバーの動作や音声はおかしなことになるはずなのだが、表現者と鑑賞者は地球上の常識という暗黙の了解の上で成立することなので、当然ながら読者の感性は物理方程式に無頓着である。
同様に、情報芸術のサイバー空間にも、空気と重力は存在しない。リアリティーを表現するのがバーチャル・リアリティーであったはずだが、仮想空間での創作が陳腐化するにつれて、現実感覚が退化しはじめる。
情報化社会の表現技法は、通常の人間感覚では対応しえない高度な情報技術のブラックボックスの上に成立している。秋葉原の無差別殺人事件などの不可解でオカルト的な犯罪が問題視されるのも、仮想と現実の間に大きな断絶を感じるからであろう。
想念と現実とは表裏のことであり、豊かな現実の体験が豊かな想念を育む。豊かで健全なコミュニケーションが成立するためには、受け手と送り手のリアルな現実体験による共通感覚が不可欠である。人間的な思索は、
色や形、光という感覚的な体験に連鎖して始まる。生活を豊かに彩る、触覚的・視覚的・身体運動的な経験からくる、驚きと喜びは、生きる興味に転換し、子供達にとって、わくわくする心のうごめきは、人間や物にたいする確かな愛着の始まりとなる。
情報芸術コースの創作は、現代の高度な表現媒体と、野生の人間感覚のギャップに注目し、根源的な身体的体験に基ずく、リアリティある豊かな仮想空間を形成し発展させようとしている。

<図版2 作者:岩本多玖海>
b. 穏やかなコミュニケーション
20世紀初頭に登場した写真と映画に影響されて、後期印象派絵画以降の芸術の有様と役割は大きく変貌した。現代のチューリングマシーンは、絵画・彫刻・演劇・演劇・文芸などの伝統的な表現領域に取って代わる新たな表現媒体をシームレスに連結し、ボーダーレスな仮想空間を拡大構築しつつある。現代における芸術の表現領域は、環境的かつ観客参加型のインタラクティブアートにまで拡大されている。
このような状況下で、19世紀的なロマン主義芸術を教条的に信奉しつづけるには限界がある。19世紀の科学思想によって拡大した、新たな人間性の、新たな連結が求められている。コペルニクスは地球と宇宙を連続させ、デカルトは人間と機械を連続させ、ダーウインは人間と動物を連続させ、フロイドは自我と無意識を連続させ、アインシュタインは原子から宇宙までの物理現象を連続させ、それぞれ人間存在の枠組みを拡大した。
生命ある者が、常に口から出し入れしている、眼に見えない空気を、なにか魂のようなものと理解していた人類が、その科学的な組成を解明したのは近代になってからのことである。元気の素である酸素は赤血球と結合し、体の隅々まで運ばれ、細胞の酸化エネルギーとなる。文脈的に考えれば、魂の生気と空気の酸素は同類項であろう。
1世紀のモザイク点描画の陰影技法をみれば、ハイライトカラー、シャードーカラー、リフレクションカラーなど、現代のCGアルゴリズムの技法とさして変わらない事に気がつく。
学生作品は、現代技術を身近で親しみやすい素材と同化させて、穏やかな技術(Calm Technology) による、コミュニティの再生 匿名的消費者との穏やかな双方向的コミュニケーションを追求している。
空中浮遊への欲望は、まず神話のメタファーによって解消され、次にダヴィンチなどの観念的機械の探求を経て、20世紀の科学実験で実証明される。しかしながら、20世紀の強力なエンジンによる飛行は「風の谷のナウシカ」の優雅な飛行とは程遠い。人類が、ピラミッドやパルテノン神殿のような堅牢な造形や、堅牢で永遠な芸術に憧れるのは、寿命も思想も風船のように儚い自分の存在が嫌だからなのであろう。

<図版3 作者:力石咲>
c .環境的コミュニケーション
白色という光の波長は無い。地球上の生物が40億年間の進化の過程で、地上に満ちていた波長の分布を、初期値の白色と認識したのである。 ゴッホの「アルルのはね橋」の日陰部分のレンガは、水面の青色を反映して水色に描かれている。水面の青色は大気のレイリー散乱による青空の反映である。一方、日向の部分のレンガは黄色い太陽のごとく彩色されている。すなわち、オブジェを描くことは、オブジェがおかれた環境そのものを描くことに他ならない。
肥大化した大脳皮質を持て余す人類は、理性とか知性とか云う妄想を巡らし、本能を制御する宗教や芸術などを発明して、仮想空間に創造エネルギー放出させてき。ところが、近代以降、行き場のなくなった創作エネルギーが、いったん物質界に向かうと、粗野な工業生産物を大量に生産し、地球環境をも破壊しはじめた。
生物の遺骸が腐敗して堆積した豊かな土壌の大地でこそ、生物の再生が営まれる。また大地は、自律直立する反力として、またマイナス電位としても絶対的に機能してきた。たかだか標高5000m、水面下50mの地球の表層でしか生息できない人類は、大地を深く掘り起こし化石燃料を手に入れ、大地のパンドラの函を開いてしまったようである。
学生作品は、古典な芸術の表現枠から環境的表現を開放し、 生態環境との相互作用、ハレの生気を日常的な現実空間に取り戻そうとしている。
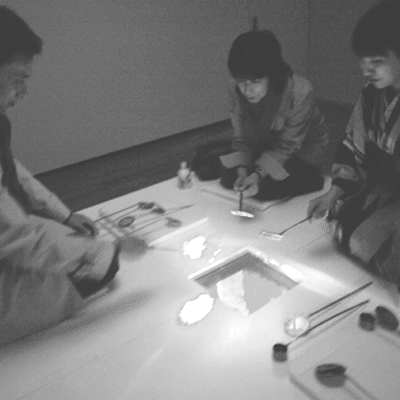
<図版4 作者:土川裕子>
4)将来に向かって
野生の人々は聖域をインスタレーションして、シャーマンが司る豊かな想念世界を共有してきたが、宗教権威に取って代わった宮廷権威は、神に替わる芸術価値を発明し、個人が収蔵して見せびらかす事のできる芸術作品を収集した。
しかしながら、芸術価値を担保してきた宗教権威・宮廷権威などの装置が19世紀に失脚し、金融権威.科学権威・民族権威などに取って代わる20世紀の現代芸術は放浪をはじめる。近代の機械的世界観による金融支配下の芸術においては、まず最初に、この世に建築される芸術の殿堂(美術館)によって、その芸術価値が担保されることとなり、1960年代には美術権威への反体制運動、1970年代には科学技術との融合、1980年代には情報化社会、1990年代にはインターネット社会などと、芸術活動の目標は揺れ動いてきた。
しかも、現代のデジタルサイバーネットが実現した情報の偏在化技術は、肥大化した大脳皮質の化学シナプスと電気シナプスを外界に漏洩し、あの世とこの世の結界を曖昧にし、情報芸術活動の目標を見えなくしてまった。現代社会において、芸術を担保する勲章を誰もくれないであろう。
従来、多摩美術大学のファインアート系学科は公募展への入選や、官立美術大学への追従を美術教育の目標とし、デザイン系学科では広告代理店や製造企業への就職をカリキュラム編成の目標としてきが、現在、目標となる画壇公募展や国立芸大などは既に存在せず、産業経済も万能ではなくなってきている。
このような状況下で、多摩美術大学は、美術の教育目標を自立的に創出して、大学自身が社会と直結する美術創作活動を展開し、美術の受け手を魅せる手段が必要である。今日、美術創作の関心は、美術館収蔵作品の制作から、現実社会での豊かなコミュニケーションの再生へと移行している。 |